近年、全国的にヒグマの出没が増加し、人身被害も深刻化しています。
このような状況下で、私たち一人ひとりが身を守るための対策を講じるとともに、地域や行政レベルでの包括的な対策も重要になってきています。
個人でできる対策
まず、ヒグマとの遭遇を避けるための「予防」が最も重要です。
- 情報収集の徹底: 山林に入る前や、居住地域周辺での出没情報を自治体やSNSなどで必ず確認しましょう。
- 特に、早朝や夕方、夜間はヒグマの活動が活発になるため、不必要な外出は控えるべきです。
- 自分の存在を知らせる: 山道を歩く際や見通しの悪い場所では、熊鈴やラジオを携行し、定期的に声を出したり手を叩いたりして、人間の存在をヒグマに知らせることが大切です。
- ヒグマは人の存在に気づくと、自ら避けてくれることが多いです。
- 単独行動を避ける: 可能な限り複数人で行動しましょう。
- 複数人での行動は、ヒグマに与える威圧感が大きく、遭遇のリスクを低減させます。
- 食べ物の管理を徹底する: キャンプや登山では、食べ物や生ゴミを放置せず、密閉容器に入れるなどしてヒグマを誘引しないようにしましょう。
- 人間の食べ物の味を覚えたヒグマは、繰り返し人里に現れるようになります。
- クマ撃退スプレーの携行: 万が一遭遇してしまった場合に備え、クマ撃退スプレーを携行し、いざという時にすぐに使えるように訓練しておくことが推奨されます。
- 遭遇してしまった場合の行動
- 落ち着いて行動する: 走って逃げると、ヒグマは逃げるものを追いかける習性があるため非常に危険です。
- 大声を出したり、急な動きをしたりせず、落ち着いて状況を判断しましょう。
- 静かに立ち去る: ヒグマがこちらに気づいていないようであれば、静かにその場を離れます。
- 距離をとる: ヒグマがこちらに気づいている場合は、視線をそらさずに、ゆっくりと後退して距離をとります。
- 体を大きく見せるために、両手をゆっくり上げて左右に振る、上着を広げるなども有効です。
- 子グマには近づかない: 子グマの近くには必ず母グマがいます。
- 母グマは非常に神経質であり、不用意に近づくと攻撃される可能性が高いです。
地域・行政レベルでの対策 - 緩衝帯の整備: 里山と人里の境界にある藪や草木を定期的に刈り払い、見通しを良くすることで、ヒグマが人里に近づきにくい「緩衝帯」を形成します。
- 電気柵の設置: 農地や家庭菜園、養蜂場など、ヒグマを誘引しやすい場所には、電気柵を設置することが非常に有効です。
- 情報共有と注意喚起: ヒグマの出没情報を住民に迅速に共有し、注意喚起を徹底します。
- 広報誌、ウェブサイト、SNS、地域内での看板設置などが活用されます。
- 捕獲と個体数管理: 人身被害につながる可能性のある個体や、人里への出没が頻繁な個体については、専門家や猟友会と連携し、捕獲による個体数管理も必要となります。
- 最近では、市街地での銃による捕獲を条件付きで可能とする法改正も検討されています。
- 地域住民の理解と協力: ヒグマとの共存には、地域住民一人ひとりのヒグマへの正しい理解と、対策への協力が不可欠です。
- 勉強会や研修会を通じて知識を深める機会を提供することも重要です。
- ヒグマ被害対策は、個人の意識と行動、そして地域全体の協力、さらに行政の包括的な支援が一体となって初めて効果を発揮します。
- 私たちはヒグマの生息地にお邪魔しているという意識を持ち、最大限の配慮と対策を講じることが求められています。

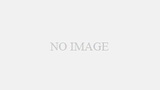
コメント